はじめに
近年、ChatGPTをはじめとする生成AIが注目を集めていますが、次に大きな飛躍を遂げるのが マルチモーダルAI です。これは 「テキストだけ」や「画像だけ」ではなく、複数の情報モードを統合的に理解・生成するAI のことを指します。マルチモーダル技術の進展により、日常生活では言葉だけではなく、画像・音声・ジェスチャーなどを組み合わせてAIとやり取りが「直感的で自然なコミュニケーション」に変化し、テキスト・図解・映像・音声を組み合わせたパーソナライズ学習で「学習や学びの喜びを支援」を提供してくれるでしょう。また、医療分野では、症状のテキス入力+画像(患部の写真)+音声(呼吸音)を総合的に判断するAI診断が導入されて「病気の早期発見や予防」が可能となり、音声が不自由な方をサポートするツールの普及などが進みバリアフリーな世界が訪れることにも期待したいものです。芸術分野では、「こんな絵を描いてほしい」「こんな音楽を制作してほしい」と声で指示すると画像や音声の新しい芸術を創造する手助けをしてくれて、今までに無い芸術分野の創造にもAIが必需品となるのではないでしょうか。
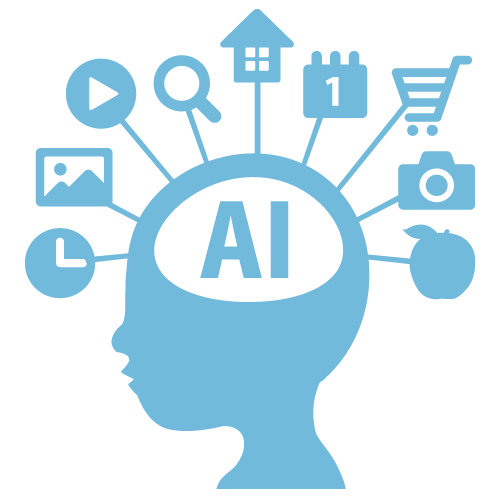
マルチモーダルAIとは?
「モーダル」とは情報の種類を意味します。
- テキスト(文章)
AIが扱うテキストデータとは、会話、記事、小説、SNS投稿などの自然言語データ、CSVやJSON形式などの構造化されたデータ、数式やプログラムコード、論文などの専門的な言語表現、画像や音声に付与された説明文やタグなどのメタデータやラベル、IoT機器やシステムが出力するログや記録データのことを指し、ここでのテキストとはAIのマルチモーダル技術を発展させるために必要なこれらのデータの総称です。テキストには画像、音声、動画はそのままだと、非構造的でわかりづらいですが、テキストは「意味を抽象化・記号化」出来るため、AI同士が理解・検索・応用しやすくなる。画像とテキストを組み合わせることで、画像の特徴量をベクトル化し、それをテキストの意味(単語、文)と対応づけることができます。例としては、写真に「猫がソファに寝ている」とキャプションを生成したり、「赤い車を探して」と入力すると画像データから該当画像を検索することが出来るでしょう。音声とテキストを組み合わせると、音声データの音響特徴に分解して、発表内容を文字起こしするだけではなく、発言者のトーンや感情をラベル化することも出来るでしょう。例としては、会議の音声から自動で議事録を作成したり、「楽しそうな声」とラベルをつけることで感情を理解したり、音声コマンドで家電製品を動かすことも出来るでしょう。動画とテキストを組み合わせることで、動画をフレーム単位で解析して、動きやシーンをテキストに要約することが出来るでしょう。例としては、監視カメラの映像で人の移動方向を認識(「人が右から左に移動している」)、YouTubeの自動字幕で動画の音声からリアルタイム翻訳・表示、テキストで指示すると動画の中から合致するシーンを自動抽出する、など日常生活、学習、仕事の効率を向上させることが出来るでしょう。 - 画像(写真・イラスト)
ここでの画像とは、写真、イラスト・CG、医療画像、文書画像、図・グラフ・チャートなどを指しています。AIはこれらの画像の数値化(ピクセル化)をおこないます。一枚の画像は縦×横のピクセル(点)で構成されており、各ピクセルには「色の情報(RGB)」が入っています。つまり、私たちがスマホやPCで見ている画像は沢山のピクセルの集合体なんです。しかし、このままの情報ではデータが大きすぎるため、AIは線や輪郭(エッジ検出)、形のパターン、質感や模様などの特徴を抜き出します。ここで使われるのがCNN(畳み込みニューラルネットワーク)で、人間の視覚野の仕組みを模倣しており、低レベルの特徴(線)から高レベルの特徴(犬の顔全体)まで階層的に理解します。階層的に理解するとは、低レベル(線、点、色の変化)、中レベル(耳、目、窓など)、高レベル(犬、建物、車)といった段階に分けてデータが何物かを理解することを指しています。次はパターン認識をおこない、特徴を組み合わせて「これは犬っぽい形」と判断し、学習データで「犬、猫、車」など大量の画像を見て特徴を比較することで分類できます。例えば、四足歩行で耳が立っている→「犬の可能性が高い」、ひげと三角耳→「猫の可能性が高い」、といったように特徴からラベル付けで確立の高い順番に判断をおこないます。マルチモーダルとの統合でテキストや音声とつながり、犬の画像に「犬」というラベル付けしてテキストに変換したり、「この犬は芝生の上に座っています」と説明文を生成することができます。スペクトログラムとは、フーリエ変換は全体の周波数を解析するだけで、「どの時間にどの周波数が出たか」はわからないので、この課題を補う方法を指しています。作り方は音声波形を短い時間ごとに分割(短時間フーリエ変換:STFT)し、書く時間スライスでフーリエ変換を実行して、時間×周波数×振動(強さ)の情報を可視化し、音声認識、音楽分析、環境音認識などに使われる技術です。見た目のイメージは縦軸:周波数、横軸:時間、色・明るさ:振動、というものになります。 - 動画(動きや文脈を含む)
動画は「時間的に連続した画像の集合体(フレーム)」で、静止画の連続+時間軸という構造を持ったデータを指しています。AIはこれらを空間的な情報(画像そのもの)+時間的な情報(動き、変化)の両方から理解します。空間的理解とは、各フレームは「普通の画像」として処理され、CNNなどで人物、物体、背景を認識して、これは画像認識と同じです。これに合わせて時間的理解は含まれるのが動画を認識するということで、動画特有のポイントは「動き」を見ることです。具体的な例では、1フレーム目は人が立っていて、2フレーム目は足が動いている、3フレーム目は前に進んでいる、このような変化を捉えるために時間的解析の仕組みが使われます。AIが使う主な仕組みは、RNN/LSTM/GRU、3D-CNN、トランスフォーマー(Video Transformer)などがあります。RNN/LSTM/GRUは動画を「時間の流れ」として理解する方法で、例えばスポーツの映像で「この人はボールを蹴ろうとしている」と予測するようなケースで使用されます。3D-CNNは画像だけでなく「時間方向(連続フレーム)」も畳み込み、動きそのものをパターンとして学習する方法で、例えば「ジャンプ」「手を振る」などのパターン化出来る動作の学習に役立ちます。トランスフォーマーは画像(空間情報)と動画の流れ(時間情報)を同時に処理することで、最近は動画用トランスフォーマーが主流になりつつある。例えば、YouTubeの自動字幕生成やこどう分析などに活用されます。これらの技術が発展することで、AIが前方カメラの動画を見て「車・歩行者・信号・動き」をリアルタイムに把握した自動運転技術、動画からスポール選手の動きを認識して戦術やフォームの分析、特定のシーンを自動で探す、フレームごとの異常+動き方の異常をチェックして内視鏡やMRI動画と組み合わせて医療分野の発展などが期待できます。
従来のAIは単一モーダルに特化していましたが、マルチモーダルAIはこれらを横断的に処理できるのが特徴です。
仕組みの基本
マルチモーダルAIは、
- 異なる種類のデータを同じ「意味空間(ベクトル空間)」に変換
同じ「意味空間(ベクトル空間)」に変換とは、マルチモーダルAIの核心部分で、テキスト、画像、音声、動画などの異なる種類のデータを、AIが同じ土俵で比べられるようにする仕組みのことを指しています。「意味空間(ベクトル空間)」とは、AIがデータを扱うときに、文字や画像はそのままでは理解できないので、全てのデータを数値ベクトルに変換して「意味を保持した数値の座標」を生成します。例えば、「猫」というテキストをベクトル[0.9 , 2.3 , 0.3 , ・・・」、猫の画像を[0.88 , 2.1 , 0.3 , ・・・」1、「ニャーという音声」を[0.99 , 2.4 , 0.33 , ・・・」と表現して、これらが近い位置にマッピングされるように学習させます。これらを同じ空間にプロットすることでベクトル空間上での近い位置にある情報を関連付けることができます。テキスト、画像、音声以外の様々なデーも例外ではありません。この技術が発展していくことで、五感でさまざまな事象を捉える人間に近い人工知能が開発されることでしょう。 - 共通の表現で関連性を学習
「共有の表現で関連性を学習」というのは、テキスト、画像、音声など異なる種類のデータを同じベクトル空間に変換して、それぞれの関連性をAIが自動で学習することを指しています。
この学習を繰り返すことで、「犬のテキスト」→「猫の画像」→近い、「犬のテキスト」→「犬の画像」→近い、「犬のテキスト」→「猫の画像」→遠い、ろいう関係せいが空間の中で自然に構築されていきます。 - 入力された複数モードを統合的に理解し、最適な出力を生成
「犬がボールで遊んでいる映像を説明して」というテキスト、画像/動画で犬が庭でボールを追いかけている動画、「取ってこい」という飼い主の音声、といった異なる形式のデータを、「犬」「遊ぶ」「ボール」というテキスト、「犬」「走る」「ボールを追う」という動画、「命令」という音声の全てを意味空間に変換して共通の土台で比較・統合できるようにします。ここで、「犬」が動画とテキスト両方に登場して同一対象と認識し、動画での行動「走る」「追う」+テキストの「遊んでいる」という行動をマッチング、音声「取ってこい!」という行動の背景(人間の指示)を理解することで、AIは「犬が飼い主にボールを取ってこいと言われている」という統合的理解にいたします。この統合的な理解を状況に応じて出力をテキスト出力、音声出力、映像生成、行動出力(ロボット制御で実際にロボット犬がボールを取ってくる)という最適な出力を選択できます。
具体的な活用事例
- 医療分野
- CT画像と診断レポートを同時に解析し、診断精度を向上。
- 教育・学習
- 教科書のテキスト+図解+音声解説を組み合わせた対話型AIチューター。
- 観光・小売
- 写真をアップロードすると、商品の説明や購入サイトへのリンクを自動生成。
- 防災・監視
- ドローンの動画+音声通報を組み合わせて状況を即時分析。
マルチモーダルAIがもたらす未来
- 人間に近い情報理解
AIにおける「人間に近い情報理解」とは、単にデータを処理するのではなく、人間が五感や文脈を使って行うような総合的な解釈に近づくことを意味します。私たちは日常生活で、視覚や聴覚など複数の感覚を同時に用いて状況を理解しています。たとえば犬が庭を走っている場面では、目で犬の姿や動きを捉え、耳で足音や鳴き声を聞き取り、さらに「犬は遊んでいるのだろう」と経験や文脈から推測します。このように人間は複数の情報を統合し、単なる事実の羅列ではなく「意味」を理解しているのです。マルチモーダルAIも同様に、テキスト・画像・音声・動画といった異なるデータを共通の意味空間に変換し、相互の関連性を学習することで統合的な理解を実現します。たとえば「犬」という文字情報と犬の画像、犬の鳴き声をすべて近い位置にマッピングすることで、それらが同じ概念を指すと理解できるのです。さらに文脈を踏まえた解釈も可能になります。試合中に「ボール!」という声が聞こえたとき、映像の状況と結びつけて「サッカーをしている」と推測するのは、人間と同じ文脈理解に近い処理です。このようにAIが複数のモードを組み合わせ、状況や意図を総合的に捉えられるようになることこそ「人間に近い情報理解」と言えます。単一の感覚に依存せず、意味を抽象化し文脈を加味した判断ができるようになれば、AIは単なる道具を超え、人間の理解力に迫る存在となっていくでしょう。 - 次世代検索エンジン
マルチモーダル技術が進歩していくと、テキストだけでなく「画像を見せて検索」「動画で問い合わせ」も実現するでしょう。今までは「テキスト」で検索するのが基本できたが、マルチモーダル検索で次世代では画像・音声・動画・テキストを組み合わせて検索するこでとが出来るでしょう。犬の画像をアップして、「この犬種は?」と検索すると結果が返ってきたり、料理の写真と「低カロリー」と入力すると該当レシピ動画が出てくるなど、人が人に問いかける感覚でAIがさまざまな情報を提供してくれるでしょう。また、単なるキーわーど一致ではなく、質問の意図や文脈を理解して答える理解(セマンティック検索)、検索結果がユーザーの過去の行動や好みに応じて出力を変え、「旅行」というキーワードで検索すると、Aさんには芸術鑑賞、Bさんにはアウトドア重視の旅行を提案してくれるでしょう。また、従来はリンク一覧だったが、次世代ではAIが直接回答や提案をしてくれる対話型エージェントに進化を遂げたり、リアルタイム統合でSNS、ニュース、学術論文、動画プラットフォームなどの複数の情報源を横断して瞬時に取りまとめて、災害時に「地震情報」と検索すると、ニュース速報、X現地報告、防災マップなどをまとめて表示してくるでしょう。つまり、次世代検索エンジンとは入方法が多様化し、検索結果はリンクの羅列だけではなく「答えや提案そのもの」になる方向に進化を遂げていくでしょう。 - 産業の効率化
マルチモーダルAI技術が進歩すると、製造・物流・医療・教育など、すべての分野で情報統合による効率化が加速するでしょう。簡単にいうと、同じ成果をより少ない資源(時間・人・エネルギー・コスト)で実現することです。つまり、「無駄を減らして、生産性を最大化する」取り組み全般を指します。製造業ではAIによる需要予測で最小限の在庫を確保し、センシング技術と融合することで故障を予知してメンテナンスを最適化して協働ロボットで単純作業を自動化することで、人間は利益を追求した設計や改善業務に集中し、農業ではドローンで農地を撮影して病害虫や水不足の場所をAIが特定、自動運転トラクターで種まきや収穫を効率化、物流ではAIが交通状況を分析して最短ルートで配送、同庫内の仕分けや運搬をロボットが自動化、需要予測に基づいた在庫管理、エネルギー分野では、AIが電力需要を予測して発電量を調整、再生可能エネルギーの変動をバランスよく供給、工場やビルの電力使用を最適化して無駄を削減、サービス業ではチャットボットがよくある問い合わせを自動対応、AI翻訳で多言語対応を効率化、店舗の売上データを分析しt絵発注や人員配置を最適化してくれるでしょう。昨今、企業の人員不足は重大な社会問題であり、日本のような環境で利益を追求するためには産業を効率化することは永遠のテーマになることでしょう。
まとめ
マルチモーダルAIは、今後のAI発展の鍵を握る技術です。
テキスト・画像・音声・動画を統合的に理解することで、これまで人間にしかできなかった複雑な情報処理を可能にします。
未来の社会では、私たちの生活・仕事・学びが 「マルチモーダルAIと共にあること」 が当たり前になるでしょう。


コメント